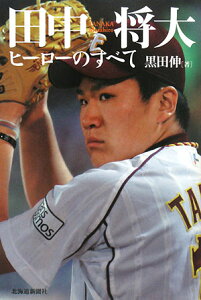高度経済成長の前夜
日本は朝鮮戦争の勃発(1950)を機とし、「糸へん景気」に沸いていた。文字通り「糸」に関わる繊維産業が、政府統制のくびきから解放されて大発展を遂げたのだった。
そんな活況にわく多くの紡績会社では、社員らが仕事の余暇として「バレーボール」を楽しめるようにとコートをつくり、そして次々と実業団チームが誕生した。
そのなかで最強を誇ったのが「日紡貝塚(にちぼう・かいづか)」。
大阪・貝塚市にある日紡の貝塚工場に集められた選手らは、敷地内にある寮に住み込み、一心、練習に打ち込んだ。
そして生まれるのが「東洋の魔女」。のちの東京オリンピック(1964)で金メダルを獲得することになる女たちである。
昭和29年(1954)に結成された日紡貝塚は、翌年には早くも日本一。昭和34年(1959)からは連勝記録をつづけていく。
その初代監督の任をうけたのが「大松博文(だいまつ・ひろふみ)」。鬼と呼ばれた男である。彼は大学時代、全国大会で2度優勝した実績を買われたのであった。
黙ってオレについてこい。
男・大松は、「泣くな!」と怒号を張り上げ、そのスパルタぶりを内外から恐れられた。
「いやー、ゾッとしましたもん」
のちの魔女の一人、宮本恵美子は高校時代、入部前の練習見学ですっかり怯んでしまっていた。
「先生の気に入らないことをすると連帯責任ですから、グランド走れってなったら、2時間でも3時間でも4時間でも延々と走らされるわけです」と、半田百合子。
「痛いって言ったって練習を休むことはできないから、言わないんですよ。ケガとか病気は休んで治すんじゃない、やりながら治すんだっていう教えだものですから」と、キャプテン河西昌枝。
■鬼
アマチュア選手は仕事もおろそかにしてはいけない。
その方針のもと、会社で資材係長だった大松は選手たちに朝8時から夕方4時まできっちり勤務に就くことを求めた。
鬼の練習はようやく仕事が終わったあとに待っている。”勤務時間を超える長い練習”はそれから始まるのだった。
「できないことやんのが練習やないかぁ!」
鬼の大松はその日の目標を定め、選手たちができるようになるまで練習をやめようとはしなかった。夜中の12時をすぎるのは当たり前。ときに練習は翌朝の日の出をみることもあった。
松村好子は言う。「練習おわるの、朝の5時ごろとかね」
体育館には始終、大松の怒鳴り声が鳴りひびく。
その最も叱られたのが谷田絹子だという。ある夜、練習で倒れる選手が相次ぐなか、谷田も倒れ伏していた。すると大松から、いきなりバケツの水をぶっかけられた。思わずコートから逃げ出した谷田。満点の夜空にむかって「大松のバカヤローーー!」と怒鳴り散らす。
谷田は言う。「すっとして体育館に入ったんですよ。大松先生に聞こえてますよね。こんなガラス一枚だから。そしたら先生、ニタニタ笑っててね。その顔見ただけで、また腹が立って(笑)」
あまりに厳しい練習は社内のウワサ話に吹かれ、ついには組合サイドまでが乗り出してきたこともあった。
「そんなことに怯むような先生じゃないですからね」と松村好子は言う。
「大松先生っていうのは、もの凄い信念もってる人です。こうだと思ったら、もう絶対に人がなんと言おうとも最後までやる」
■おじょう
信念の鬼、大松博文。
しかし意外にも、少年時代は”引っこみ思案のおとなしい性格”だったという。ついたアダ名は「おじょう」。
「お嬢さんの”おじょう”です。それぐらい優しかったんでしょうね」と、当時を知る人は語る。
”おじょう”を”鬼”にかえたのは、戦争だった。
第二次世界大戦の開戦直後に出征した大松は、中国を歴戦し、最後はビルマでインパール作戦に小隊長として従軍する。部下は年上ばかり。自らが人の嫌がることや危険な任務を率先してやらなければ、年上の部下らは動かなかった。
「人に任せられんちゅうことを学んだんでしょうなぁ。自分でやらなきゃとにかく納得できないっちゅう」。大松の軍時代を知る人はそう言う。
実際、日紡貝塚でバレーボール部を率いるようになった大松は、コーチをまったくおかずに、たった一人で選手たちにボールを打ち続けた。
キャプテン河西昌枝は言う。「私たちは汗でびしゃびしゃになれば着替えたりしましたけど、先生は汗をふくひまもなく着替えるひまもなくビタビタになりながら、連続して打ってるわけです」
そんな一心なる大松の姿に、選手らは次第に惹かれていく。
河西は続ける。「そういう姿を見てると、自分のためじゃない、誰のためじゃない。選手のためを想ってやってるのが分かるから。先生にしてみれば、何とかこの選手をうまくしてやろうと思って打ってるのを、選手がわかるから」
チームと監督の絆は、無言のうちにも養われていった。
「このチームが強かったのは、それなんですよ」とキャプテン河西は言う。
月に一回は”息抜き”もあった。大松が選手らを連れて外へ遊びにいくのだ。
松村好子はその思い出を語る。「かならず月一回、映画つれてってくれるんです。全員でバーッと難波へ出て、ほんで映画みて、帰りは『おまえら、好きなん食べよー』っていうてくれるんです」
(バケツで水をかけられた)谷田の記憶では、遊んで帰ったあと夜10時からでも練習がはじまることがあったというが…。
■世界
高度経済成長まっしぐらの昭和30年代。”豊かさ”が手の届くところにまで迫っていた当時の人々は、がむしゃらに生きていた。
そうした中、東京オリンピックの開催が決定した。アジアで初めてのオリンピックである。
しかしオリンピック開催決定の当初、バレーボールはまだオリンピックの正式種目ではなかった。バレーボールにとって世界最高峰の舞台は「世界選手権」だった。
そして、当時の王者は「ソ連」。昭和35年(1960)の第3回世界選手権で、日本代表は決勝まで駒をすすめるものの、王者・ソ連に敗れる。日本は、その高さとパワーに圧倒された(代表メンバー12人中、日紡貝塚6人)。
宮本恵美子はこう語る。「もう、凄かったですよ。(ソ連は)体格的に違いますもん。背は高いし、ガッチリしてるし、男かなと思うような感じ。いやぁ、これだけ違うかなと思った」
「打倒ソ連」
ソ連に敗れて以来、それが日本バレーの至上命令となった。
「世界選手権でソ連を倒す」
■回転レシーブ
「おまえら、ゴロゴロ転がってみぃ」
大松には、打倒ソ連へむけた”ある秘策”があった。
「そっから、ぽっと起きてみぃ」
そう言われてヨイショと立ち上がる選手たちに、大松は「そうやない」と言う。”起き上がりこぼし”のように、コロンと立ち上がれと言うのだった。大松は、子どもの遊ぶオモチャをみて新技「回転レシーブ」を思いついたのだという。
「なぜ、こういう回転レシーブをするかといいますと…」、大松はメディアに語る。「次の動作に敏捷にうつれるように、こういう回転をしては、また所定の位置に敏捷にかえるというための練習であります」
打倒ソ連へむけた回転レシーブ。ソ連の猛攻を凌ぎ切るには、「守るに守るしかない」と大松には思われた。ゆえに、練習のほとんどがレシーブの練習に費やされた。
そして、その練習はやはり過酷であった。大松は以前にも増して容赦なく、選手たちにボールを浴びせかける。
「ぼんぼんぼんぼん、投げられるわけすよ。まだ転んでるときにもボール投げられて、『こんなの誰がどないしても上げられんやないか!』という気持ちになってきたら、もうカーッてなって、私」
思わずカッとなった谷田絹子は、”蹴っちゃいけないボール”を足で蹴るや、大松にぐーっと食ってかかったという。それほど、選手らは大松に追い詰められていた。
大松は言い放った。
「むこうが100、練習してるんなら、体力が劣る分、150%練習せなあかん。ソ連が10なら、お前らは15、17練習せいっ!」
■東洋の魔女
昭和37年(1962)、ついに世界の頂点をかけて、ソ連と雌雄を決するときがやってきた(第4回・世界選手権モスクワ大会)。
苦杯をなめさせられた2年前と同じく、決勝のカードは「日本 vs ソ連」。
大松と選手たちは、この2年間、この場でソ連を倒すためだけにすべてを賭けてきた。
しかし、さすがソ連は強い。
第一セット序盤、日本はリードするものの徐々にソ連のパワーに圧倒されていき、このセット、ついには競り負ける。
コートチェンジの際、大松は選手らに声をかけた。「お前ら、会社で練習した回転レシーブを思い切ってやれ」と。
以後、厳しい練習に耐え抜いて身体に染み込んでいた回転レシーブが、要所要所で決まっていく。勢いに乗った日本は、そのまま3セットを連取。
日本はソ連をセットカウント3対1でやぶり初優勝。
悲願の世界一に輝いた。
「日本列島のミステリーだ!」
ソ連のマスコミは、驚くように書きたてた。
「魔法使いのようだ!」
ソ連の世界選手権4連覇をはばんだ日本。ソ連を不動の王座から引きずり下ろした衝撃は、「東洋の魔女」という言葉を世界に知らしめることになる。
■正式種目
すべてはやり遂げた。
この世界選手権での優勝を手土産に、大松も選手たちも「引退」するつもりだった。
そんな気持ちで、モスクワからの帰り道、優勝プレゼントの世界一周旅行を魔女たちは無邪気に楽しんでいた。
ところが…、帰国した彼女たちを待っていたのは、思わぬ知らせ。
「2年後の東京オリンピックで、バレーボールが正式種目に決まりました!」
報道陣は魔女らにそう告げ、金メダルへの期待を露骨にあらわした。
「えーーっ!?」
彼女らの脳裏に浮かんだのは、あのツラい練習だった。「もう、終わったと思っていたのに…」
半田百合子は、げんなりした。「なんでまた365日、夕方の4時半ぐらいから練習して、終わるの夜中の1時、2時でしょ。休みなしでしょ。もう、またあと2年かって…。こんな堪忍してくれって」
最年長だったキャプテン河西(当時29歳)も即答はしかねた。「じゃまたあと2年やりますって、そう簡単には返事ができなくて…。それからすったもんだ。やめるのやめないの、やるのやらないの(笑)」
「結婚か五輪か」
適齢期”東洋の魔女”日紡貝塚
予想つかぬ二年先
(大阪日々新聞 昭和37年)
金メダル確実とみられていた”東洋の魔女”が、東京オリンピックに出場するか否か。
それは社会問題にまでなっていった。
■キャプテン河西昌枝
キャプテン河西の両親は心配していた。娘はもう29歳。親の願望としてはやはり結婚してほしかった。末っ子だったからなおさらだった。
こうした話には大松も鬼ではない。彼はなにより選手たちに将来、しあわせになってほしかった。
大松は言った。「これ以上やれとは俺からは言えない。しかし、君たちがやるなら、俺もやる」
キャプテン河西は、悩んだ末に答えをだした。
「まぁ29で結婚しても、31で結婚しても変わりないか、みたいな(笑)。そう思って、結婚よりもバレーボールを選びました」
”あの河西”にそう言われると、他の選手らもやめるわけにはいかなくなった。
そして、また始まった。
地獄の日々が。
大松は叱咤した。「今までの練習の”倍の倍”もやらないとダメだ!」
半田百合子は冷や汗を流した。「なんかゾーッとしました(笑)」
恐ろしいことに練習時間はさらに伸び、大松の厳しさは一段と増していた。
大松のみならず、キャプテン河西までもが「鬼」となっていた。仕事で一足遅れてくる大松に代わり、選手たちにボールを打ち続けたのは彼女だった。
松村好子は言う。「先生より厳しかった(笑)」
大松の場合は厳しいといえど、どこか甘えられた。
松村は言う。「先生だったら、一本ぐらいミスしてもいいか、息抜きしたれっていう甘えがあるんですよ。でも、河西さんの場合は夢中でした。怒られたら怖いから(笑)」
■新人
東京オリンピックの金メダルにむけ、攻撃力強化のために一人の新人が加わっていた。
磯辺サタ(19歳)。高校No.1アタッカーであった。
しかし、そんな鳴り物入りの彼女でも、魔女らのなかに入ればぺーぺーにすぎぬ。まったく周りについていくことはできなかった。
キャプテン河西は容赦なく、「足手まとい」と磯辺に言い捨てた。
先の先を読んでプレーしていた中、磯辺のところにボールがいくと、その先が予測できず、後手後手にまわらざるを得なかった。
新人・磯辺は言う。「あんたがいないほうが楽だって言われましたよ(笑)。わたし一回ね、練習中に廊下にでて、5分くらい大きな声でワンワン泣いて帰ったんですよ。練習さぼって」
正気にもどった磯辺が、監督のもとへ謝りにいくと、大松は「バカなことすんな…」と優しく言ったという。それで「すごく気が楽になりました」と磯辺は振り返る。
両親のいなかった磯辺にとって、大松は父親的なものを感じさせる男であった。ほかの選手らも然り。大松は「男」として魅力的であった。
宮本恵美子は言う。「背は高いでしょ。精悍な顔してますよね。で、あんまりベラベラしゃべらない。みんなの面倒をみてくれる。結婚するんだったら大松先生みたいな人と結婚したいな、と私は思ってましたもの。先生が嫌いだったら、あの練習にはついていけませんよね」
■全国行脚
大松は、練習の緊張感をさらに高めるために、北は北海道から南は九州、日本全国で公開練習を敢行した。
キャプテン河西は言う。「どこの体育館いっても満員なんですよ。で、満員であればあるほど、ものすごく厳しいことをやるわけです(笑)」
”東洋の魔女”に国民が寄せる「金メダルへの期待」。公開練習を通じて、それが選手たちにビンビン伝わってくる。
観るほうも同様、「あんな厳しい練習をやってるんだから、勝ってほしい、勝たせてやりたい」という切なる思いが募る。
いつしか、国民と選手らの気持ちは一つに近づいていっていた。
そして昭和39年(1964)、いよいよオリンピックが東京にやって来た。
快晴の国立競技場。
灯される聖火。
入場行進の最前列には、女子バレーボールの選手たち。
彼女らの目が見据えるのは、ただソ連のみ。
ふたたびソ連との因縁の対決が迫っていた。
■決戦前夜
日本とソ連の実力は、他国から抜きん出ていた。
初戦、日本はアメリカを軽々と下し(15-1, 15-5, 15-2)、ソ連もルーマニアに圧勝(15-5, 15-6, 15-0)。
以後、日本はルーマニア、韓国、ポーランドに順当に勝利を収め、ソ連もまた、1セットも落すことなく日本との直接対決(決勝)を迎えた。
新聞は、東洋の魔女による目覚ましい活躍を報じる。
「当然の勝利。サァ、”金”で有終の美(日刊スポーツ)」
国民は皆、「金メダルは確実だ」と思っていた。
しかし、当時マネージャーとしてチームと接していた小島孝治は、そうは思っていなかった。
「余裕はあったと言うけど、ウソですなぁ。大松さんは変動なかったけど、選手はね、だんだんと目は血走ってくる。考えもだんだん焦ってくる」
谷田絹子は当時をこう語る。「口には出さずに、『負けたらどうしよう、日本にはおれんかもしれない』とかね。どっか山の中に籠って、みんなから逃げ出してしまいたいっていう、そういう気持ちがほんとにありました」
それでも谷田は、足首を捻挫してなお、ソ連との対戦を渇望してもいた。
「このために練習してね、一生懸命やってきたんだから。テーピンをして、痛み止めの注射をしながらソ連戦に出たんですよ。大松先生がメンバーチェンジと言われても、私はポールに食らいついてでも(コートの)外に絶対に出ないと思ったもの(笑)」
■決戦
1964年10月23日、決戦の日。
試合直前、大松は選手らに言った。
「今までワシの言うことを聞いて、よく頑張ってくれた。これが最後だからな。頑張ってくれるな」
宮本恵美子は言う。「みんな胸にグゥっときてね」
東洋の魔女、最後の戦いの幕が切って落された。
実況「ニッポンの河西、回転レシーブ、拾った! さあ、磯辺!」
一時は「足手まとい」とまで罵られた磯辺サタは、オリンピックでは立派なエースにまで成長していた。セッターのキャプテン河西は、勝負所では決まって磯辺にボールを集めた。
実況「磯辺のスパイク! 決まったー!」
練習につぐ練習で、練りに練られた日本にスキはなかった。
さすがのソ連も浮き足立つ。日本は順調に得点を重ね、2セットを連取。つぎの第3セットをとれば、夢にまでみた金メダル。
試合は大詰め。
第3セット、「14対9」と日本はソ連を追い詰めた。
「あと一点」
金メダルまで、あと一点。
■あと一点
5点もの差をつけてマッチポイントを迎えた日本であったが、この土壇場でソ連の猛攻に火がついた。
王座奪回を目指すソ連は、国家の強力なバックアップを得て日本のプレーを徹底的に研究していた。まさに国家を威信をかけた戦いだったのだ。
実況「ルイスカル、打った!」
ソ連のエース、ルイスカルのスパイクが光る。決まる。ルイスカルに集められたボールは、次々と日本のコートに決まっていく。
じりじりと差を詰めるソ連。
実況「おーっと、サービス・エース! 13点目であります。さすがに粘ります。ソビエト」
スコアはついに「14対13」。まさかの追撃に日本は不安定なプレーを連発してしまっていた。
キャプテン河西は言う。「なんかフッとこう、気の緩みというのかな。そんな時にミスが連続して。普段やらないようなミスが出たりしましたよね」
「あと一点」がとれないニッポン。
選手らはすっかり浮き足立っていた。
しかし、ベンチの大松は微動だにしなかった。どっしりと落ち着けた腰はそのままに、口はぐっと結んだままだった。
彼にはもう口を出す気がなかった。すべてを選手たちに任せていたのだった。
その監督の泰然とした様をチラと見て、キャプテン河西は理解した。
「私はもう全然冷静にしていて。大丈夫だからって。私は笑いもしないし、あんまり表情も崩さないから(笑)」
そのキャプテンの落ち着きぶりは、選手たちに伝わった。
半田百合子は頼もしさを感じていた。「やっぱりキャプテンは、ああいう時は強いかなぁ。やっぱりリーダーシップっていうのかな」
■最後
実況「バックトス。磯辺のスパイク。今度は宮本のスパイク。ソビエトもよく受けました。ルイスカル! とった。磯辺! ニッポンです。バックトス。磯辺! またとりました。ルイスカルだ。宮本、磯辺。」
「14対13」からの長い長いラリー。
宮本恵美子は言う。「いやもう、拾って拾われて、拾っては打ちしてね」
それを制したニッポン。ようやく流れを引き戻した。
そして、6回目のマッチポイント。
ついにその時はやってくる。
最後にソ連は前がかりすぎたか、手が出た。オーバーネット。
実況アナウンサー、鈴木文彌は叫んだ。
「ニッポン、優勝しました! ストレートで勝ちました。ニッポン、優勝しました! ニッポン、金メダルを獲得しました!」
感慨を込めて、鈴木は続ける。「苦しい練習につぐ練習。すべて”この一瞬”のために払われた涙ぐましい努力。厳しい練習に耐え抜き、青春をボール一途に打ち込みましたのも、みんな”この一瞬”のためであります」
※視聴率は66.8%を稼ぎだしていた。
欣喜雀躍する選手たち。
しかし、大松ばかりはベンチから立とうともしなかった。いくら選手らに手をひかれても、そこを動く気はないようであった。
娘たちのような選手たちが歓喜する光景を見やりながら、大松はひとり寂しさを感じていた。すべてが終わったという寂しさを。
いちばんの叱られ役だった谷田絹子の想いも、また似たようなものだった。
「その瞬間は金メダルをとれた嬉しさじゃなくて、『もうこれでみんなとお別れかな…』って。うん。その涙のほうが強かったですね」
メインポールには、高々と日の丸が掲げられた。
大松は、表彰台に上に立った選手たちを、静かに見ていた。
彼女らの胸には金メダルが輝いた。
大松の元に戻った選手らは、大松に金メダルをかけようとした。だが、彼はそれを拒んだ。
宮本恵美子は言う。「金メダル、もらわないんですよ、先生は。だから、『先生にかけてあげたいです』って言いましたよね。『親よりも兄弟よりも自分よりも、大松先生にあげたいです』って」
■後日
オリンピックの熱狂が去るとともに、大松博文は監督を引退。
最年少の磯辺サタをのぞいた東洋の魔女5人(河西昌枝、宮本恵美子、谷田絹子、半田百合子、松村好子)も、あとに続いた。
東洋の魔女の強みであった司令塔、キャプテン河西昌枝は、オリンピックの翌年に日紡を退社。そして、2歳年上の自衛官と結婚した。
大松博文は、中国の首相・周恩来の招きで中国の女子バレーを指導することとなった(その後、中国は世界一の座につく)。
名門・日紡貝塚というチームは、東京オリンピックでマネージャーを務めていた小島孝治・新監督に受け継がれ、公式戦258連勝を記録した。以後、チーム名が「ユニチカ」となり、2000年の活動停止をもって「東レ・アローズ」へと引き継がれた。
東京五輪の金メダルを目指していた頃の魔女らは、当時、こんな歌を口ずさんで自らを励ましていたという。
♪やるぞ見ておれ 口には出さず
世界制覇の一途な夢を
負けてなるかよ くじけちゃならぬ
そうだ今年は東京五輪
乙女 望みを貫くときにゃ
敵はソ連だ こちらは日紡
なんの世界は怖くはないが
鬼の大松 練習がつらい♪
大松博文は昭和53年(1978)、57歳で他界。
墓石の脇には、「根性」の文字が刻まれた”石のバレーボール”が捧げられている。

(了)
関連記事:
「中国と戦う夢」。脱・根性バレー、眞鍋監督
男社会に船出する砕氷船。女監督・中田久美(女子バレー)
メダルの次は「お嫁さん」。杉本美香(柔道)の潔さ
ソース:ドキュメント『スポーツ大陸』
「東洋の魔女 鬼の大松 コートの絆」