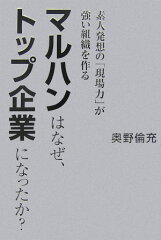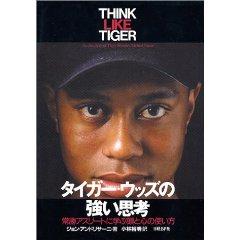「Le JAPON par IPPON(日本の『一本勝ち』)」
こんな見出しがフランス紙(レキップ)に踊った。
それはサッカー日本代表がフランスを1対0で破ったことを報じたものだった。「まさに『一本のカウンター』で、レ・ブルー(フランス)を沈めたわけだ」。
その勝利は6度目の対戦にして初。最後に負けたのは、0-5という歴史的にして屈辱的な大敗であった(2001年3月)。
「一回のチャンスを一発で決めたんだから、日本はたいしたチームだよ」
試合後、フランスのFWカリム・ベンゼマはそう語った。彼の言う通り、試合内容はフランスが圧倒。ボール保持率はフランスがおよそ6割。放ったシュートの数は、フランスが日本のおよそ4倍である(23対6)。
盛んにシュートを打ったフランス(枠内15本)が日本ゴールを割ることができなかったのは、ひとえにGK川島永嗣がビッグ・セーブで耐え抜いたからでもあった。「あれだけチャンスをつくったのに、日本のゴールキーパーがスーパーセーブを連発するもんだから、一点も決められなかった(フランスMFブレイズ・マテュイディ)」。
勝つには勝ったが、内容では負けていた。日本代表の選手たちは、そう感じていた。
とりわけ酷評されたのは、前半のプレーである。
「日本はとてもナイーブで、若い子羊というか、まるでU-21代表チームのようだった」と、11年前に日本を5対0で破った時の左サイドバック、ビセンテ・リザラズは振り返った。「本当に酷かったし、言い訳のしようがない内容だった」。
日本代表のザッケローニ監督は、「シャイ過ぎた」とその前半戦を評している。
フランスの激しいプレッシャーに怯んだ日本。簡単にボールを下げしまい、慌ててミスが生じる。セットプレーではフランスの高さと強さに翻弄され、危険なシーンをつくられてしまう。
その戦い方は「強敵に向かうチャレンジャーの姿」からはほど遠く、「守備のための守備」を強いらるばかりであった(前半のシュート数はフランス12本に対して、日本はわずか1本)。
ところが後半戦、「ハーフタイムのロッカールームで何があったのか?」と思わせるほどに日本代表は豹変。「まるで飛行機の急上昇のように、あっという間に日本は地上から3000mの高みにまで到達した」。
「後半だけを見れば、日本は世界のどの国とも戦い得るし、いわゆるサッカー大国との差も限りなく縮まっている」と前半を酷評したビセンテ・リザラズも舌を巻くほど。「僕が現役の頃(10年前)、日本の選手は単純なフェイントにも引っかかっていたのに…」。
「その瞬間」は最後の最後に訪れた。
後半43分、右サイドを疾走してきた長友佑都がパスを受けると、そのまま中へ折り返す。そこに飛び込んできたのは香川真司。日本の「一本」が決まった瞬間だった。
日本代表の特徴のひとつ、「攻撃のための守備」が遺憾なく発揮された後半戦。ザックジャパンの武器であるサイドからの効果的な攻撃が、自陣深くからのカウンターを炸裂させたのである。
もし、後半戦のような戦い方が常にできるのであれば、「日本が2年後のワールドカップ(ブラジル)で、準々決勝に進むのは、そう難しくはないと僕は思っている」と、かつてのフランス代表ビセンテ・リザラズは締めくくった。
フランスに食らった歴史的な大敗から10年以上が経ち、「日本も世界からリスペクトされるチームになりつつある(ジョルジーニョ元ブラジル代表)」。
日本にプロサッカーができてから20年、「今日では多くの日本人がヨーロッパでプレーするようになった。メンバー表を見ても、半分以上がヨーロッパのクラブに所属し、ブンデスリーガでプレーする選手が7人もいる」。
次のワールドカップまで、あと2年。
希望の芽は確実に膨らんできている…。

ソース:Sports Graphic Number (スポーツ・グラフィック ナンバー) 2012年 11/8号
「歴史的勝利を呼んだ勇気とバランス」