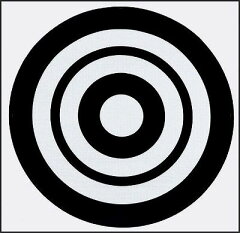「正直、『年俸』を提示されたときにはビックリしました。『0』を一つ数え間違っちゃった」
そう言うのは、バレーボールの「木村沙織」。それも仕方がない。その年俸はゼロがずらりと並ぶ「100,000,000(1億)円」。日本女子スポーツ界に、ついに「一億円プレーヤー」が誕生したのである。
バレーボール選手の年俸は、ごく一部の選手が1,000万円台に手が届くだけで、普通は200〜500万円くらいが相場だという。かつて、ある女子ゴルフ選手が「バレー選手になる気持ちが分からない」と問題発言をしたほど、バレー選手は「低年俸」だったのである。
そこに木村沙織の「年俸・一億円」の一報。
日本バレーボール界の常識はひっくり返った。
その驚きの額を提示したのは、世界最高峰のバレーリーグを擁する「トルコ」であった。トルコには世界各国から「大砲」クラスの選手たちが集まっており、世界の有名選手がキラ星のごとく在籍している。そのリーグ戦はまるで「毎試合が国際試合」だ。
そのトルコが一億円払ってまでも是非欲しいと言ってきた選手、それが日本のエース「木村沙織」であったのだ。
当の本人は、いつもどおり「ホンワカな笑み」。まるで「陽だまりのタンポポ」のよう。
その柔らかさからは、バリバリのアスリートの印象は薄い。先輩の竹下佳江も、「ほのぼの」という印象を語っている。その一方、全日本に招集されたばかりの木村を「才能って凄いなぁ」とつくづく感心して見ていたという。
当時、急遽ピンチヒッターとして招集された木村は、試合によってセッター、ブロッカー、レフト、ライトと「猫の目のように変わるポジション」を、どれもヒョイヒョイとこなしていたのだという。身長が高い選手はレシーブは苦手なはずなのに、「うそーっ、このボール上げちゃうの?」という好守で、先輩の竹下をたびたび驚かせていた。
「私、『努力』ってしたことがないんです」と、のほほんの木村。
しかし、それは彼女が努力を努力と思っていないからである。「出来ないことがあったら、出来るまで練習するのは『当たり前』。苦手なプレーは得意になるまでやる。これって当たり前のことだから、努力とは違うでしょ?」と木村。
先輩の竹下もこう続ける、「ほのぼのとしている割には、苦しいことにも耐えられる根性もあるんです」と。
ただ、「玉にキズ」は木村の「穏やか過ぎる性格」にあった。高い実力を持ちながらも、その自覚が薄く、自らがエースとなった時も、やはり穏やかなままであったのだ。
そんな木村に、監督の眞鍋政義氏は「喝」を入れる。「お前が崩れたら、全日本は負けるんだぞ!」と。
それでも木村は、当初、監督の言っている意味が理解できなかった。「バレーはチームスポーツなんだから、1人の選手の出来不出来が結果を左右するなんて思っていませんでした。『この監督は何を言ってるの?』って感じで…」
眞鍋政義氏が全日本の監督に就任したのは2009年。いまやすっかり「IDバレー」で有名となった。その眞鍋監督は得意のデータを示して、木村に各試合を分析してみせる。「だから、負けた」、「だから、勝った」との説明を何度も何度も繰り返した。
「眞鍋さんと何度も話しているうちに、『自分の立場』が少しずつ染みこんできました。チームの期待に応えなきゃって、腹がドンと据わりました」
腹の据わった木村は、2010年の世界選手権でその強さを見せつける。相手チームがエースの木村を潰そうと徹底的に狙ってきたが、「たとえミスをしても、平然としていた」。その結果は堂々の「銅メダル」。
オリンピックを2年後に控えた世界選手権での銅メダルは、日本チームを勢いづかせた。いよいよ、「遠くに霞んでいたブラジル、アメリカの2強の尻尾」が視野に入ってきたのである。
ところが、日本チームは焦りすぎた。攻撃のスピードを一気に上げていったその途端、木村のタイミングはすっかり狂ってしまった。
「もう頭の中がシッチャカメッチャカで、しまいには、助走が右足からか、左足からかも分かんなくなっちゃいました」と、木村は大粒の涙をこぼす。「人前では泣くな」と母から厳しくしつけられていたのに…。木村は苦しくて仕方がなかった。
ロンドン五輪の最終予選は、目標の1位通過どころか、「最後の一枚の切符をやっと手にいれる体たらく」。オリンピックの予選ラウンドは、3勝2敗で何とか通過。木村のギアは依然として低いままだった。
そして迎えた運命の「中国戦」。眞鍋監督がずっと「勝負どころ」だと言い続けていたこの一戦、ついに木村のスパイクは爆発する。
「アーーッ」と雄叫びをあげて打つ木村。そんな声は今まで聞いたこともなかった。中国の2枚ブロックもモノともせずに吹き飛ばす。「幅広いコースに強打を放ち、時にはライン際にポトリ」。
結局日本は、この死闘をフルセットで制することになる。木村の得点はじつに33を数えていた。

「ブロンズ・メダリスト、ジャパン!」
オリンピックで28年ぶりの銅メダルを日本にもたらしたエースは、掲揚される国旗を万感の思いで眺めていた。
「だって、日の丸の隣りに、ブラジルとアメリカの国旗が上がっているんですよ! やっとこの2大強豪国の隣りに来れたんだなぁって」
1984年のロサンゼルス五輪以来、日本はメダルから遠ざかっていた。「東洋の魔女」はアメリカやブラジルがどんどんと進化させる技術とスピードにすっかり置いてけぼりだったのだ。アジア勢では、唯一高さのある中国だけがその争いに加われていた。
そのスピードを追いかけるあまり、木村は一時スランプに陥るものの、チームメイトの「スピード戻そうか?」という提案には、決して首をタテに振らなかった。あくまでも、世界のスピードで勝負することに木村は固執したのだ。
悩み続ける木村の話をよく聞いてくれたのが竹下佳江だったという。
「なぜか、テンさん(竹下)には話せたんです」
ブラジルに敗れた後の3位決定戦。韓国を破りメダルを決めた、その歓喜の瞬間、木村をまっさきに抱きしめたのは、その竹下だった…。
木村の凄さは、点取り屋のエースにも関わらず、抜群に高い守備力も持ち合わせていることだ。オリンピックでベスト・スコアラーBest3のうちでも、木村ほどレシーブができた選手はいなかった。
世界に豪腕アタッカーは多しといえど、「守備」もできる選手となると極端に少ない。打つも良し、守るも良しの木村に世界が注目したのは、当然のことだった。
彼女はまさに「一億円プレイヤー」として相応しい選手だったのだ。
「ホントは海外があまり好きじゃなかったんですけど…」と語る木村は、他の海外チームから一億円以上のオファーがあったにも関わらず、「トルコ」を選んだ。それは、金額の多寡よりも「環境やリーグのレベル、活性度」を優先した結果だった。
トルコは全てプロリーグ。その資金は潤沢であり、世界の代表選手がトルコに結集している。そして、2020年のオリンピック招致に向けて、国民全体が女子バレーに期待を寄せているのである。
木村と同年齢には、サッカーの本田圭佑、長友佑都、大リーグのダルビッシュ有など、世界的な選手が数多い。そんな刺激も彼女の海外移籍を後押ししたという。
いまのバレー選手は、企業のOLと同賃金であることが多い中、木村の年俸は突出している。「バレーだけじゃなく、他の競技の選手も『スポーツで食べていける』ようになれば嬉しいなと思います」と語る木村。「バレーは低年俸」という悪しき常識に風穴を開け、スポーツ選手のプレー環境を良くしたいという想いも、その胸にはあった。
木漏れ日のような「穏やかな笑顔」の彼女は今、新天地のトルコで新しい花を咲かせようとしている…。

関連記事:
指を骨折していたセッター「竹下佳江(バレーボール)」
お腹の空いた「さすらいのリベロ」佐野優子(女子バレー)
「和」こそが日本バレーの底力。栗原恵
出典:
Sports Graphic Number 2012年 9/27号
「木村沙織 一億円プレーヤーの決意」